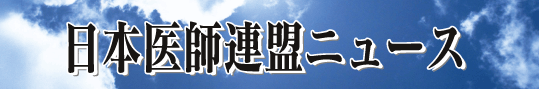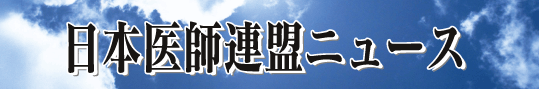|
今日の医療界を取り巻く環境は、診療報酬の改定をはじめとして、一連の「医療制度改革」等について、まさに逆風が吹き荒れているというのが実情である。
そのような状況下において、われわれの声を何としても国政に反映させるためには、実効性の面から、一人でも多くの自由民主党所属国会議員に、現下の医療問題に関する認識を的確にもってもらうことが焦眉の課題となっている。
従来であれば、一部の有力厚生労働関係議員に対し理解を得、根回しを行うことにより概ね目的が達する状況であったが、小泉純一郎政権においては、一方的な官邸主導型政策決定色が強くなり、これを打破するためには、一昨年十二月の国民医療推進協議会主催の「混合診療解禁阻止」運動あるいは今回の「高齢者の患者負担増反対」運動のように、一人でも多くの国会議員の方(一昨年は、衆・参国会議員三百二十名の方に紹介議員となっていただき、「混合診療解禁阻止」の請願を衆・参両院本会議において全会一致で採択)に、医療問題に対する認識をもっていただくことが不可欠になっている。
そこで、各都道府県小選挙区担当責任者等と地元選出自由民主党国会議員との懇談会を昨年に引き続き企画・実施したものである。
もちろん、各都道府県も、県・郡市区段階においてこの種の企画を実施されていると思われるが、まさにこの厳しい状況下において、各都道府県医師連盟と日本医師連盟が一体となり、自由民主党所属国会議員に対して医療問題の認識を深めてもらうための場づくりが不可欠と判断したものである。
この懇談会は、各都道府県小選挙区ごとに三名の役員(総括責任者一名、担当責任者二名)を選出いただき、当該選挙区選出の自由民主党国会議員と膝を突き合わせた懇談会を企画したものである。原則として毎週水・木曜に開催し、時間的には二時間、最初の一時間は日医が抱える当面の諸課題につき、各都道府県医師連盟役員と日本医師連盟役員相互の認識を深める場とし、後の一時間は、各選挙区ごとに、それぞれの選挙区選出自由民主党国会議員との理解を深める場とした。
質疑応答(要旨抜粋)
本懇談会は、三月九日(木)までに六回開催されたが、その懇談会においての主要質疑応答は次のようなものである。
- タバコ税の増税については、一箱千円の値上げで数兆円規模の増収になる。予防のための検診・肺がん対策等には莫大な医療費がかかることから、財源の一部をそれらの負担費に充てることは考えられないか?(神奈川県)
*今日までも、自由民主党の税調等に強く働きかけてきたが、残念ながら、今次国会で決定したのは、一箱たった二十円の値上げで、かつ児童手当に充てるというものであった。今後とも、実現に向けて全力を傾注したいと考える。
- 救急車の利用につき、実態的には必要度の低い人の利用が目立つこと等から、一部有料化を考えるべきでは?(神奈川県)
*大変難しい問題である。世界で、救急車が無料なのは基本的に日本のみであり、これを高く評価する面もある。したがって、今後慎重に検討して参りたい。
- 産科医の減少が大幅であり、神奈川県下においても切実な問題となっている。解決策を模索しているが、なかなか現実的なよい案がない状況である。このことを国会議員は知っているのか?(神奈川県)
*どうすれば解決できるのかは、極めて難しい問題。処遇のアップだけで解決できるものではないが、今次の診療報酬改定において、少しはアップがはかれると考えている。なお、産科医は医事紛争が多いことや、看護師が内診できないこと等問題が山積しており、このことをぜひ国会議員に訴えてほしい。
- 今次国会で成立する「医療制度改革法案」は今後不安の種であるが、日医連として、今後具体的な行動・対策は何か考えているのか?(愛知県)
*今日までも、自由民主党社会保障制度調査会幹部に集まっていただき徹底した議論を行い、また有力な厚生労働関係議員には個別に陳情を繰り返す等できることはすべて実行したつもりであるが、結果としてなかなか当方の思惑どおりに動かなかったというのが実情である。今後の国会審議の場においても、可能な限りの問題点の究明をさせるべく、最大限の努力を行っていきたいと考えている。
- 今次診療報酬改定により、領収書の発行義務が出てくるのか?(愛知県)
*支払い側は「算定したすべての点数項目がわかるレセプト形式のものを無償で発行すべき」と強く主張していたのに対し、結果的に、点数表の各部単位(初・再診料、在宅医療、検査等)で金額の内訳がわかる領収書を無償で交付することとなった。具体的な運用要領については、今後厚生労働省と協議を行う予定なので、その段階で明らかにして参りたい。なお、患者からの質問が多い「指導料」は「管理料」に変更した。
- 日医は、高齢者医療の案を出していたが、今次改正案にはその趣旨は盛り込まれているのか?
また、法改正に当たっては、日医に充分な相談はあったのか?(愛知県)
*「後期高齢者医療制度」は、概ね日医と同じものである。なお、今次医療制度改正関連については、基本的には厚生労働省からの事前相談といったものはなく、一方的に厚生労働省が案を作成し、成文化しているのが実情。
- 今後、小泉総理大臣の政策決定方式に対してどのように対応していくつもりなのか? また、最近厚生労働関係議員の声が小さいのでは?(静岡県)
*自由民主党の厚労部会では、大部分の議員が反対しているにもかかわらず、官邸の意を受けたトップ層がそれを押し切っているのが実情である。また、従来の厚生労働関係議員のなかにも、むしろ小泉改革を積極的に推進しようという議員もおり、今後これらの総点検が必要。
- 先般の署名活動は、今後どのように活用されていくのか? また、前回のように、より効果的な、国会議員の紹介を受けたうえでの「請願」方式をとらず、衆・参両議院議長への「陳情」方式にしたのはなぜか?(静岡県・沖縄県)
*国会議員の紹介を得ての「請願」方式は、国会開催期間の会期末(今次国会開催の場合ならば六月末)にしか取り扱いがなされず、署名の目的からはそれでは時期を逸してしまうことから、衆・参両議院議長宛の「陳情」方式としたものであるが、千七百万を超える署名は、必ずや今後の医政活動面において大きな役割を果たすものと考えている。
- この種医政関連の懇談会を、ぜひ地元でも開催していただき、日医連役員と地元医師連盟役員との意思疎通に役立ててもらいたい。(静岡県)
*医政活動は時間をかけてじっくり行う必要があり、一朝一夕にはなかなか難しいものである。この企画は、現在の小泉総理大臣のトップダウン方式を打破するために、ボトムアップ方式の必要性があることを痛感して実施しているものであり、必ずや役に立つものと考えている。日医連としてできる限りの協力はするつもりなので、この種懇談会をぜひ地元においても開催していただきたい。
- 昨年の衆院選で、日医連は議員の推薦を地方の自主性に任せるとの方針であった。その結果、民主党を支持するケースが全国的に目立った現象となり、結果として多大の混乱を引き起こすこととなったが、時の政権政党でない民主党をなぜ支持することを許容したのか?(岡山県)
*日医連としては、自由民主党を支持することはゆるぎない方針である。しかし、地方の自主性も尊重し、民主党議員の推薦を受け入れたのは、過去の日医連も実施していたものであり、決して新たな方針ではない。そのケースは少数であり、過去にくらべてとくに増加しているわけではなく、ご理解賜りたい。
- 郵政法案審議の時に、植松執行部は、武見・西島議員に対し、反対するようにプレッシャーをかけたとの新聞報道がなされたが、真偽は?(岡山県)
*二月二十四日付メディファックスに、植松執行部としての記者会見記事が掲載(「唐澤氏の選挙パンフレットによると、郵政民営化をめぐって現執行部が武見氏らに反対票を投じるよう指示したとされるが、植松会長は『私たちには送り出している母体としての立場があり、相談して決めてほしいとは言ったが、反対票を入れろと言った覚えはない。事実誤認』と説明【要旨】」)されているので、ぜひご理解賜りたい。
- 国家予算のなかで、社会保障費のパイを増やす案を日医では考えているのか?(茨城県)
*世界中で、わが国の社会保障費の水準は低水準であり(「国民負担率の国際比較」において、わが国は三五・九%、米国三二・六%、英国四七・七%、仏六三・七%等)、この点を政府に強く訴えているところである。
- 介護保険法等の一部改正により、現在三十八万床ある療養病床が、十五万床に縮小されるが、患者の具体的受け皿なくして法律改正が進んでいるのを、日医はいかに考えるか?(沖縄県)
*受け皿を明確化することなくこのような法律改正が進むことに、日医は今日まで絶対反対の姿勢で臨んできたが、残念ながら法文化されてしまった状況である。しかしながら、今後とも問題点の把握・指摘をはかりながら国会審議を見守って参りたいと考えているので、ぜひご理解・ご協力を賜りたい。
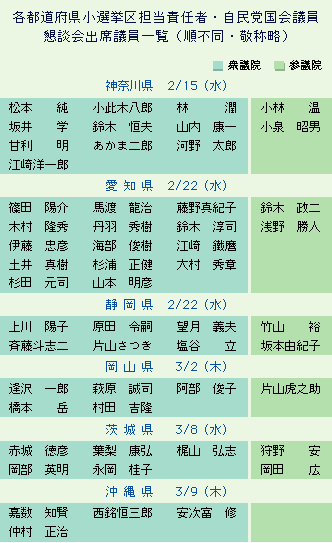
|