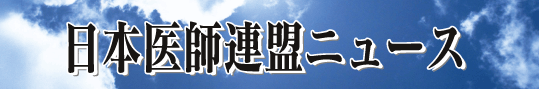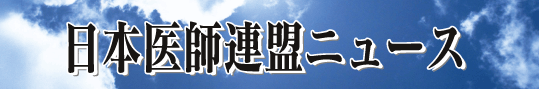|
分科会A 医政活動の広報活動について
| 分科会A |
 |
分科会Aでは、三上裕司常任執行委員が司会を担当して開会。
日医連としての広報活動を活発化する上で、連盟会員に限らず、連盟会員でない医師、医学生に対してもPR活動が重要であるといったことが中心に議論された。主だった意見として、「日医連に入っていない医師に対しても、日医連に入ることの必要性を訴えかけていく」ことが挙げられた。
また、「会員のなかで医政活動について意識が低下しているのではないか」という意見もあった。それに関しては、医政に対する意識を高めるために、委員会を立ち上げて活動している地域もあった。「会員にもっと医政について興味を持ってもらうために、意識向上委員会を設けてもいいのではないか」といった声も上がった。
同様に、医学生に対しても日医連についてアピールしていく必要があるのではないかといったことが、意見としてあった。「大学の教員のなかにも日医連に入っている先生は多いので、医学生に対して、医政活動の必要性についてのアピールをもっと積極的に行ってほしい。また、どのようにアピールしていくべきかの指針がほしい」との意見もあった。
日医連に対して「誰がどのように意思決定をしているのかといったことが、末端の会員には見えてこない。ホームページや記者会見を通じて知らせているとはいえ、一会員としては、よくわからない」といった意見も多数寄せられた。
分科会B 世論に訴えかけていくことの重要性について
| 分科会B |
 |
分科会Bにおいては、司会を今村聡常任執行委員が担当し、鈴木邦彦常任執行委員も会に参加した。
いかに国民の世論を喚起して訴えかけていくのかということについて議論が深められ、「マスコミを通じて国民に訴えかけていくことが大事である」といった意見が出た。
「今回の参加者のなかでも、医政活動に関する理解や活動について温度差があるので、意見交換をする機会をもっと設けることが大事である」といった提案もあった。
また、「日医連が政党を推していくのか、それとも国会議員個人を推していくのかといったことの意思統一が成されていないのではないか」といった意見もあった。
日医連への提言として、「今、医療で問題とされていることがなかなか会員に伝わらず、会員の参加意識が低迷しているのではないか」といった意見があった。
これに対して、今村聡常任執行委員は、「ホームページや記者会見等を通じて情報の発信に努めているが、よりきめ細かく情報を発信できるように考えていきたい。現在の日本の医療というものが、法律によって定められており、医療制度をよりよいものにしようとすれば政治との関わりが重要になってくるといった認識を持っていただければと考えている。また、日医から流す情報を、県や地域から個人へ伝達するシステムについて、地域のほうでも検討を重ねてほしい」との要望を述べた。
分科会C 医療の専門家集団としての情報発信について
| 分科会C |
 |
藤川謙二常任執行委員を司会者として、Cグループは開催された。
Cグループでは、政党にとらわれず、議員個人に対して活動することが重要ではないかといった意見が出ていた。また、日医連に対して理解ある国会議員の先生を増やし、そういった議員の先生方を通して医政活動を行っていくことが大切であるといったことが、共通認識として形成された。
さらに、「日医連は医療の専門家として、国民や議員に対して医療を伝えていくことが大事なのではないか。若い医師の先生のなかには政治に対してアレルギーをもっている方も多いが、そういったアレルギーをなくしていくことが大事である」といった意見があった。そのためには、日医連から会員に対して一方通行に情報発信するのでなく、会員の方からの意見を吸い上げていく場所を設けるだけでも変わってくるのではないかといった意見もあった。それに対して、「医療問題の情報を共有するためのツールとして、Facebook(フェイスブック)などのITの利用や、テレビ・書物を利用して情報発信を行っていくのがいいのではないか」といった提案があった。
最後に、「我々はプロ集団として、国民や国会議員に医療情報を伝えていかなければならない。そういったことを踏まえて、これからの医政活動を頑張っていきたい」との発言もあった。
各分科会における発表事項
分科会最後には、各分科会の代表者が会の内容をまとめて発表を行った。
各分科会に共通していたこととして、「日医・日医連が今、どのような取り組みをしているのか、また、どのような問題があって、それに対して日医はどのように考えているのかといったことを広く共有する必要がある」といったことが挙げられた。
日常における診療も公的な制度で決められており、国民の医療をよりよくするために陳情活動をしていくことは、とても大切である。そのためにも「国会議員と人間関係をつくり、顔の見える関係を保って、継続的に意見交換をしていく必要がある」ことなどが再認識された。
|